立川市の散歩コース【6.西砂川と殿ヶ谷分水跡を歩く】
西武立川駅を出発し、神社や分水跡を巡るコースです。
散歩コース概要
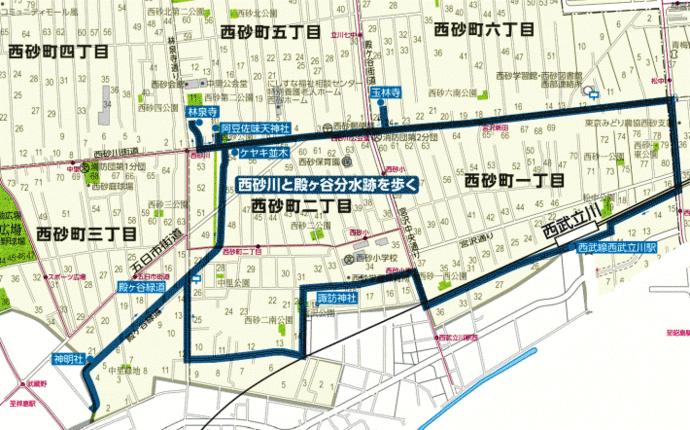
諏訪神社

宮沢新田は享保年間(1716~1736)の初期、殿ヶ谷分水を利用して、宮沢村(現在の昭島市)の人々によって開発されました。
諏訪神社は、親村(※)であった宮沢村の氏神様を勧請したものです。
祭神は建御名方の命(たけみなかたのみこと)。
境内には眼病に霊験あらたかという小祠があります。
(※親村:新田開発のためにやってきた人々の出身地の村)
殿ヶ谷緑道

享保5年(1720)、現在の西砂町、殿ヶ谷、宮沢、中里の新田開発のため、玉川上水から殿ヶ谷分水が引かれました。
殿ヶ谷分水の跡地を、その痕跡を残しながら遊歩道にしたものが殿ヶ谷緑道です。
神明社

神明社は中里新田の鎮守として享保3年(1718)頃に創建され、当初は「神明稲荷社」と称していました。
その後、近くにあった愛宕社と合併し「神明愛宕社」となり、後に神明社となりました。
享保年間の初期に川崎村(現在の羽村市)の中里伊兵衛が、殿ヶ谷分水を利用して中里新田を開発しました。
神明社は中里地域の氏神、祭神は天照皇大神(あまてらすおおみかみ)で、以前は中里新田の西端にありましたが、横田基地の拡張により現在の場所に移転鎮座しました。
林泉寺

林泉寺は享保14年(1729)中里新田の人々の菩提寺として創建されました。
春になると桜が美しく咲きます。
山号を鷹尾山といい、臨済宗建長寺派の寺です。
『新編武蔵風土記稿』には福生市にある「清巌院」との関連が記されています。
阿豆佐味天神社

殿ヶ谷新田は殿ヶ谷村の人々によって開発されました。
阿豆佐味天神社は、殿ヶ谷村にある本社から氏神様として勧請した神社です。
砂川四番にある鎮守阿豆佐味天神社は兄弟社です。
境内には殿ヶ谷分水記念碑があります。
玉林寺

玉林寺は山号を嶺雲山といい、臨済宗建長寺派の寺で、普済寺の末寺です。
殿ヶ谷村に創建されましたが、殿ヶ谷新田の人々の菩提寺として、元文年間(1736~1741)にこの地に移されました。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 教育部 生涯学習推進センター 文化財係
〒190-0013 立川市富士見町3-12-34
電話番号(直通):042-525-0860
ファクス番号:042-525-1236
教育委員会事務局 教育部 生涯学習推進センター 文化財係へのお問い合わせフォーム

